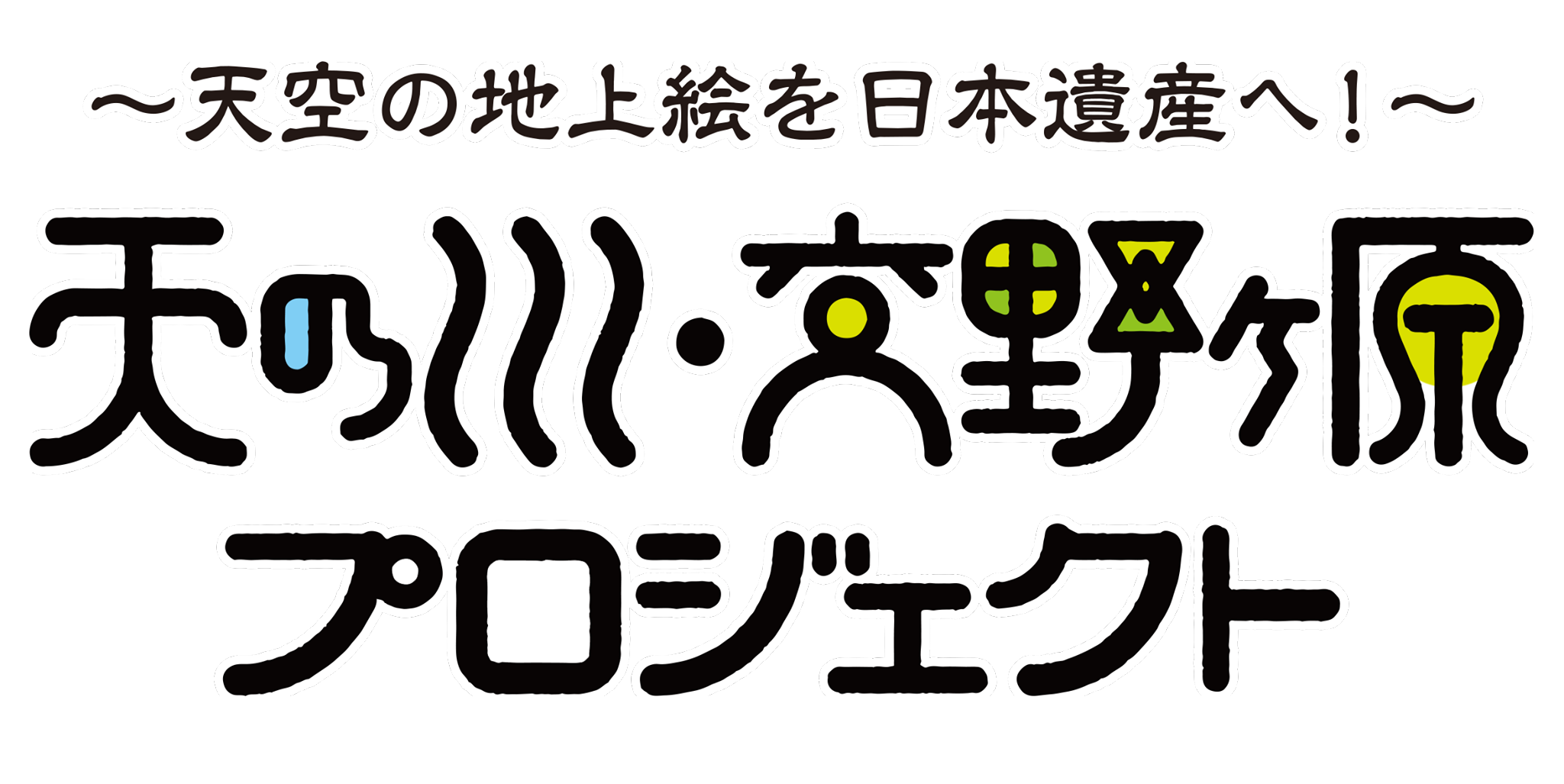さて、蓮如上人の記事に続いまして、若干モヤっとしている、交野ヶ原の中世シリーズ。
今回取り上げるのは、南北朝のことです。
応仁の乱以降続く、下克上の戦国時代よりも、天皇家を2つに割ったという意味では、混乱の極みだったと言える南北朝時代。
その時代に、活躍した、楠木正成は河内出身の豪族でありながら、後醍醐天皇に登用してもらったことを恩に思い、最後までご奉公する忠臣として知られています。

河内出身で全国ファンも多い大楠公
ただ、私が今回取り上げたいのは、その楠木正成の三男であり、父と兄が亡くなった後、棟梁として南北朝の和平直前まで生きた楠木正儀です。

粋な武将の楠木正儀
というのも、塩野七生さんの「ローマ人の物語」という作品に下記のような表現があります。
ローマ人は、政治の失策を修復するのに、軍事でごり押ししてその結果を泥沼化するよりも、政治的なやり方で修復するほうを選んだのである。
(中略)
闘う大義名文は失われても、闘ううちに芽生えた憎悪は残る。憎悪さえあれば、そしてそれに火を点ける指揮官さえいれば、戦争は続くものなのだ。
この言葉を南北朝事態に置き換えてみれば、鎌倉幕府を倒したものの、政治的にも軍事的に2勢力にわかれ、そのまま硬直状態に陥ったのは、政治的失敗です。
争いを始めた世代が亡くなってしまえば、大義名分は失われ、対立関係だけが残ってしまい、日常化した「戦うこと」だけが目的化していく。そういう状態はある意味、ニヒリズムに支配されていく時代だとも言えます。
その中で、武力を誇りながら、粋と美学を貫き、政治的決着に動いたのが、楠木正儀だったと考えます。
バサラ大名とのやり取りに見えた粋
こういう時代になると、ただ戦うことに意味はなく、いかに戦うかということが重要になってきます。
南朝でそういった武将が楠木正儀であり、北朝では、「バサラ大名」といわれた、佐々木道誉でした。

バサラ大名
この二人は終始ライバル関係であったようですが、非常に印象的なエピソードがあります。
「太平記」によると、楠木正儀が京都を攻め落とした際、佐々木道誉の屋敷に陣を構えたそうです。その際、道誉は使用人などはそのままにし、宴会などができる状態にしていたそうです。
その後、楠木正儀が京都を追われる時は、佐々木道誉の屋敷の使用人などはそのままにし、略奪も行わず、それどころか、自らの宝刀を置いていったと言われています。
「武力で勝つだけでは仕方なく、風流がわかるのだよ、俺たちは」
そういった粋な男たちの声が聞こえてきそうです。しかし、そういう形を大事にする男たちだからこそ、南北朝を終わらせる政治的な調整ができたのでしょう。人の心を掴めなければ、政治の形は整えることができません。
燃えてしまった、楠木正儀の過去帳
そんな、楠木正儀の過去帳が、楠葉に残って「いました」
楠葉にある、久親恩寺に残っておりました。
私も気になって、ここのお寺に電話してみたんです。
そしたら、「先般の火事の際に、焼けてしまったのです」
何?と思って調べると、下記の記事がヒットしました。
非常に残念でした。枚方市の教育委員会にも問い合わせましたが、写しなどは残っていないそうです。
「名が残れば過去帳など気にするものか」という正儀の高笑いが聞こえてきそうな気もしますが、伝承や資料というものは細々とでも残していかないといけないのだなと改めて思わされる出来事でした。